民主主義の危機に対し、熟議民主主義で解決策を探る

国際コミュニティ学部 准教授 小須田 翔(コスダ ショウ)先生
早稲田大学大学院 政治学研究科 博士課程単位取得満期退学
修士(政治学)
専門分野:政治学
主要研究テーマ:政治理論、政治哲学、民主主義論、熟議民主主義論
自分たちのことを自分たちで 決める社会の実現に近づくために
規範的政治理論という方法
私は現代政治理論、特に規範的政治理論を専門に研究しています。この分野は、政治に関わる概念を分析し、あるべき政治の姿を問う学問領域です。そうすることによって、現実の政治制度や実践に対して批判的に考察することができるようになります。例えば、自由という概念を深く掘り下げ、理想的には人々が社会においてどのように自由であるべきかを明らかにすることで、現在の日本社会のどこに自由に対する抑圧があるのかといったことを考察することができるようになります。政治に関わる概念は多数ありますが、私の主な関心は民主主義にあります。民主主義は現在、危機に陥っていると言われています。危機とは、欧米諸国でのポピュリズム*¹の台頭、選挙で選ばれたリーダーが民主的な制度を破壊してしまう「権威主義の台頭」、AIやSNSなどの発展と混乱によって人々が事実に基づいて意見交換をすることが難しくなっている状況などをさしています。
民主主義の危機という事態にどう対応するか?
こうした「民主主義の危機」に直面するとき、私たちはどうすればいいのでしょうか。私が注目しているのは、民主主義のあるべき姿として「熟議民主主義」がふさわしいのではないかという考え方です。熟議民主主義とは、人々が投票やその他の政治的行動を起こすときに、互いに対話し、他者の意見を尊重しながら正当化し合うプロセスを重視する民主主義の理論です。政治に意見の対立はつきものですが、自分とは異なる立場の人とよく話しをしてみると、「なるほど、一理ある」と思えることもあるのではないでしょうか。そのような過程を重視するのが熟議民主主義の特徴です。この特徴をよく表現している言葉として、アメリカの哲学者であるジョン・デューイが次のように述べています。「民主主義で大切なことは、多数派がどのように投票したのかという事実よりも、多数派がどのように多数派になったのかである」。つまり、最終的には多数決で決定するとしても、その前に色々な人の考えを聞いて皆でよく考えてから決めようということです。
熟議民主主義の成果
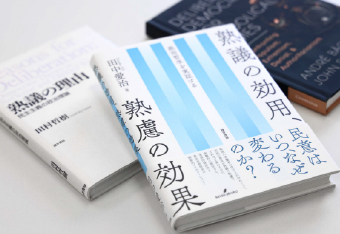
田中 愛治 編
『 熟議の効用、熟慮の効果』 / 勁草書房
田村 哲樹 著
『 熟議の理由』 / 勁草書房
この熟議民主主義論は、研究者の理論にとどまらず、実際の政治やまちづくりにも大きな変化をもたらしてきました。過去30年以上にわたって、日本を含む世界各地で、重要な公共的問題について話し合うために実際に人々が集まり、熟議民主主義を実践しています。その好例が、ヨーロッパにあるアイルランドで実施された市民会議です。アイルランドでは、複雑な宗教的背景の下で、人工妊娠中絶の合法化や同性婚の是非といった社会を二分するようなデリケートな問題がありました。この問題の解決のために用いられたのが、熟議を活用した市民会議です。市民会議では、国民から無作為抽出された参加者が、専門家の情報提供を受けながら、数ヶ月にわたる話し合いを重ねました。話し合いの中で互いに異なる意見を交換することで、参加者が自身の考え方を修正していく過程が見られました。その結果、中絶合法化や同性婚の容認という結論を導き出し、その後の国民投票で可決される大きな要因となりました。これは、熟議という考え方が社会の根深い対立に挑戦し、変化を生み出した画期的な事例と言えます。
規範的な価値の実現
こうした熟議民主主義の意義を踏まえ、私は次の二点に関する研究を進めてきました。一つ目は、熟議に参加する人々は、規範的政治理論の想定する姿にどれほど近づいているのかという問題です。すなわち、熟議に参加する人々は、社会の複雑な問題に対して十分に理解した上で決断を下すことができているのでしょうか。また、熟議に参加する人々は、平等に話し合うことができているのでしょうか。実際は高齢で社会的地位の高い男性ばかりが話していたということでは、民主主義の理念である平等な参加とは言えません。そこで私は、ミニ・パブリックスと呼ばれる小規模な熟議の場に関する先行研究を分析しました。その結果、参加者が政治的知識を深めていることや、自らの意見を修正したりしていることが幅広く確認できることが分かりました。他方で、参加者の属性に偏りが見られる場合もありました。特に、参加者が高齢の男性に偏ることがあり、社会における不平等をある程度は反映してしまうことがあるということもわかりました。これは、熟議民主主義の規範理論*²が想定する平等といった価値が、実際の話し合いの場では十分に実現していない可能性を示しています。とはいえ、こうした偏りは、話し合いの場の設計や進行方法などの工夫次第で改善の余地があると考えています。
未来世代の包摂
二つ目の研究課題は、民主主義という決定方法が未来の人々とどう関わっているのかというものです。民主主義国家は様々な決定を下しますが、その中には遠い未来に生きる人々に対して深刻な影響を及ぼす決定が含まれます。例えば、環境政策や財政政策などです。しかし、こうした決定の話し合いに参加するのは現在に存在する人々だけです。未来の人々は、自分たちに大きな影響を与える政策の話し合いには参加することができません。とりわけ、多くの先進国が採用しているリベラル・デモクラシーという制度は、直前の業績を過大評価しがちな選挙や、代表者の数年間の任期制によって、短期的な思考を強めてしまう傾向があると指摘されています。「自分たちのことを自分たちで決める」という民主主義の理念からすると、ここには大きな問題があります。この問題に対し、選挙ではなく話し合いを中心とする制度へと改革すれば、現在の人々であっても長期的な影響を考慮することが可能になり、未来世代の利害関心を取り込んだ決定に近づくことができると考えられています。私は、熟議における「理由の提示」という特徴が、未来の人々への責任を果たすための一つの手がかりになるのではないかという仮説のもと、研究を進めています。
こうした研究を通して私が一貫して考えているのは、「現代の大規模で複雑な社会において、人々が自分たちのことを自分たちで決めることはどのようにして可能なのか」という問いです。これは、「民主主義の危機」が叫ばれている社会において、避けて通れない問いだと考えています。今後も、この問いを解き明かすべく研究を進めていきます。
*1 政治エリートや制度を批判し、普通の市民の意志を直接政治に反映するべきと主張する政治運動。
*2 規範的政治理論のこと。ここでは熟議民主主義の望ましいあり方に関する理論をさす。
こうした研究を通して私が一貫して考えているのは、「現代の大規模で複雑な社会において、人々が自分たちのことを自分たちで決めることはどのようにして可能なのか」という問いです。これは、「民主主義の危機」が叫ばれている社会において、避けて通れない問いだと考えています。今後も、この問いを解き明かすべく研究を進めていきます。
*1 政治エリートや制度を批判し、普通の市民の意志を直接政治に反映するべきと主張する政治運動。
*2 規範的政治理論のこと。ここでは熟議民主主義の望ましいあり方に関する理論をさす。




