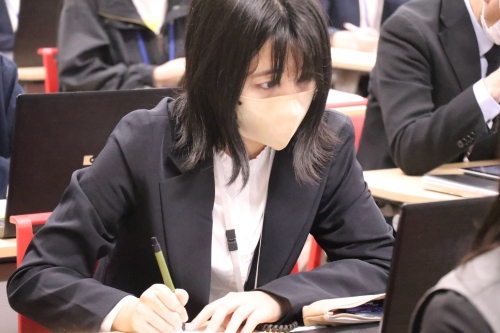2025.05.27
中学
高校
2025年度 教職員研修会4/23「授業改善」、5/14「生成AI」を開催しました
4月23日(水)
「授業改善~生徒の主体性を育む授業の実現に向けて~」

2025年4月23日(水)の教職員研修会では「授業改善」について行いました。
本校では「生徒が自ら考え学ぶ考えやすい授業」を目指し、教員が一丸となって授業改善に取り組んでおります。この取り組みは、「生徒の主体性を育む授業」の実現を目指すものです。
研修では、一年間を通して目指す授業の姿として掲げている「生徒が自ら考え学ぶ考えやすい授業」、すなわち「生徒の主体性を育む授業」を実現するために、具体的にどのような授業を展開していくかについて深く議論しました。特に、本校が授業改善において重視する「考えさせる」視点と「教え合う」視点に焦点を当て、教科ごとに集まって、それぞれの教科でどのようにこれらの視点を取り入れ、生徒たちの主体性を育んでいくかについて、具体的な授業法を含めて熱心に話し合いました。これは、教科ごとに「考えやすい授業」とは何かを明確にするという目標のもと行われたものです。
本校では「生徒が自ら考え学ぶ考えやすい授業」を目指し、教員が一丸となって授業改善に取り組んでおります。この取り組みは、「生徒の主体性を育む授業」の実現を目指すものです。
研修では、一年間を通して目指す授業の姿として掲げている「生徒が自ら考え学ぶ考えやすい授業」、すなわち「生徒の主体性を育む授業」を実現するために、具体的にどのような授業を展開していくかについて深く議論しました。特に、本校が授業改善において重視する「考えさせる」視点と「教え合う」視点に焦点を当て、教科ごとに集まって、それぞれの教科でどのようにこれらの視点を取り入れ、生徒たちの主体性を育んでいくかについて、具体的な授業法を含めて熱心に話し合いました。これは、教科ごとに「考えやすい授業」とは何かを明確にするという目標のもと行われたものです。




この研修で話し合われた内容を踏まえ、今年度は年間を通して授業改善に取り組んでまいります。1学期は、生徒に「考えさせる」土台を作る「スタート期」と位置づけ、教科内での授業観察や振り返りを集中的に行いながら、具体的な授業法の試行錯誤を進めます。その後、2学期の「発展期」には、生徒自身の「気づき」や「振り返り」を重視し、協働的な学びを深める取り組みへと発展させていきます。そして3学期の「まとめ期」では、学んだことを「言語化」し、他者に伝えることを意識したアウトプットを通じて、生徒たちが協働的かつ自立した学びを評価できることを目指します。
このように、本校では教員一人ひとりが常に学び続け、生徒たちにとって最も良い学びの場を提供できるよう努めております。生徒たちが主体的に学びに向かい、互いに協力し合いながら成長していく姿を、ぜひご家庭や地域でも見守っていただけますと幸いです。
今後とも、本校の教育活動へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
このように、本校では教員一人ひとりが常に学び続け、生徒たちにとって最も良い学びの場を提供できるよう努めております。生徒たちが主体的に学びに向かい、互いに協力し合いながら成長していく姿を、ぜひご家庭や地域でも見守っていただけますと幸いです。
今後とも、本校の教育活動へのご理解とご協力をお願い申し上げます。


5月14日(水)
「生成AI~教育現場における可能性と課題を探る~」

2025年5月14日(水)の教職員研修会では、株式会社MOMOの柿塚様と石松様をお招きして「生成AI」についてご講演をいただきました。 変化のスピードが速い現代において、「なぜ今、AIなのか?」という問いは、もはや常識を置き去りにするほど重要なものとなっています。AIは「足りない手を補う“もう一人のスタッフ”」や「時間とお金を生み出すツール」になり得る可能性を秘めています。教育現場においても、大学生の約半数が生成AIを継続的に利用しており、東京都では全ての都立学校に生成AIサービスが導入されるなど、その活用は広がりつつあります。 今回の研修では、企業のAI導入を支援されているプロフェッショナルチームである株式会社MOMO様から、柿塚様と石松様を講師にお招きしました。株式会社MOMO様は、学校法人を含む150社以上のAI導入支援実績をお持ちです。
研修では、まず生成AIの基本的な概念や、従来のAIとの違いについて学びました。生成AIは、決められたタスクを実行する従来のAI(サポート)とは異なり、「0から1を生み出す」あくまで人間の補助的な役割であり、単体で100%のものを作るツールではないことを確認しました。
また、学校教育における生成AIの具体的な活用方法についても多くの示唆を得ました。例えば、教員の授業資料作成のサポートとして、目的に合わせた構成案の作成や、パーソナライズされた資料作成が可能です。生徒に対しては、問題の解答だけでなく、詳細な解説や効果的な学習アドバイスを提供する学習サポート、また、カウンセリング支援や面接対策の支援として活用することで、生徒たちのメンタルケアの充実や、面接準備の効率化、自信向上に繋げられる可能性が示されました。さらに、多言語対応の面では、外国人学生へのバイリンガル教材作成や、リアルタイムの会話サポートにより、言語の壁を越えたグローバルな学習環境の構築が期待できます。
一方で、生成AIの利用にはリスクと対策が不可欠です。特に、生成された情報が常に正しいとは限らないため、出典の確認や事実関係の検証、著作権処理の留意が必要です。また、生徒の氏名や住所、保護者情報などの機微な個人情報を入力しないこと、入力データの最小化や使用するサービスのプライバシーポリシーの確認など、個人情報保護への最大限の配慮が求められます。研修では、これらのリスクを理解し、安全に活用するためのチェックポイントについても学びました。 今回の研修を通じて、教職員一同、生成AIが教育にもたらす可能性と、適切に活用するための知識・心構えを深めることができました。AIと「協働」する時代においては、AIが出せる「答え」だけでなく、「何を問いとして設定するか」、そして「こんな未来が良い!」「こんな社会にしたい」といった願いを持つこと、考える力、創造力、課題設定力が鍵となります。そして、AIには「生成できない」、親や兄弟、生まれ持った体力や知能、名前、経験といった「貴方に固有なもの」、すなわち人間性や個性がますます貴重になります。
本校では、今回の研修で得た知見を活かし、生徒たちがAIと共存するこれからの時代を力強く生き抜くために必要な力を育んでいけるよう、教育活動に生成AIを効果的かつ安全に取り入れる方法を探求してまいります。
研修では、まず生成AIの基本的な概念や、従来のAIとの違いについて学びました。生成AIは、決められたタスクを実行する従来のAI(サポート)とは異なり、「0から1を生み出す」あくまで人間の補助的な役割であり、単体で100%のものを作るツールではないことを確認しました。
また、学校教育における生成AIの具体的な活用方法についても多くの示唆を得ました。例えば、教員の授業資料作成のサポートとして、目的に合わせた構成案の作成や、パーソナライズされた資料作成が可能です。生徒に対しては、問題の解答だけでなく、詳細な解説や効果的な学習アドバイスを提供する学習サポート、また、カウンセリング支援や面接対策の支援として活用することで、生徒たちのメンタルケアの充実や、面接準備の効率化、自信向上に繋げられる可能性が示されました。さらに、多言語対応の面では、外国人学生へのバイリンガル教材作成や、リアルタイムの会話サポートにより、言語の壁を越えたグローバルな学習環境の構築が期待できます。
一方で、生成AIの利用にはリスクと対策が不可欠です。特に、生成された情報が常に正しいとは限らないため、出典の確認や事実関係の検証、著作権処理の留意が必要です。また、生徒の氏名や住所、保護者情報などの機微な個人情報を入力しないこと、入力データの最小化や使用するサービスのプライバシーポリシーの確認など、個人情報保護への最大限の配慮が求められます。研修では、これらのリスクを理解し、安全に活用するためのチェックポイントについても学びました。 今回の研修を通じて、教職員一同、生成AIが教育にもたらす可能性と、適切に活用するための知識・心構えを深めることができました。AIと「協働」する時代においては、AIが出せる「答え」だけでなく、「何を問いとして設定するか」、そして「こんな未来が良い!」「こんな社会にしたい」といった願いを持つこと、考える力、創造力、課題設定力が鍵となります。そして、AIには「生成できない」、親や兄弟、生まれ持った体力や知能、名前、経験といった「貴方に固有なもの」、すなわち人間性や個性がますます貴重になります。
本校では、今回の研修で得た知見を活かし、生徒たちがAIと共存するこれからの時代を力強く生き抜くために必要な力を育んでいけるよう、教育活動に生成AIを効果的かつ安全に取り入れる方法を探求してまいります。